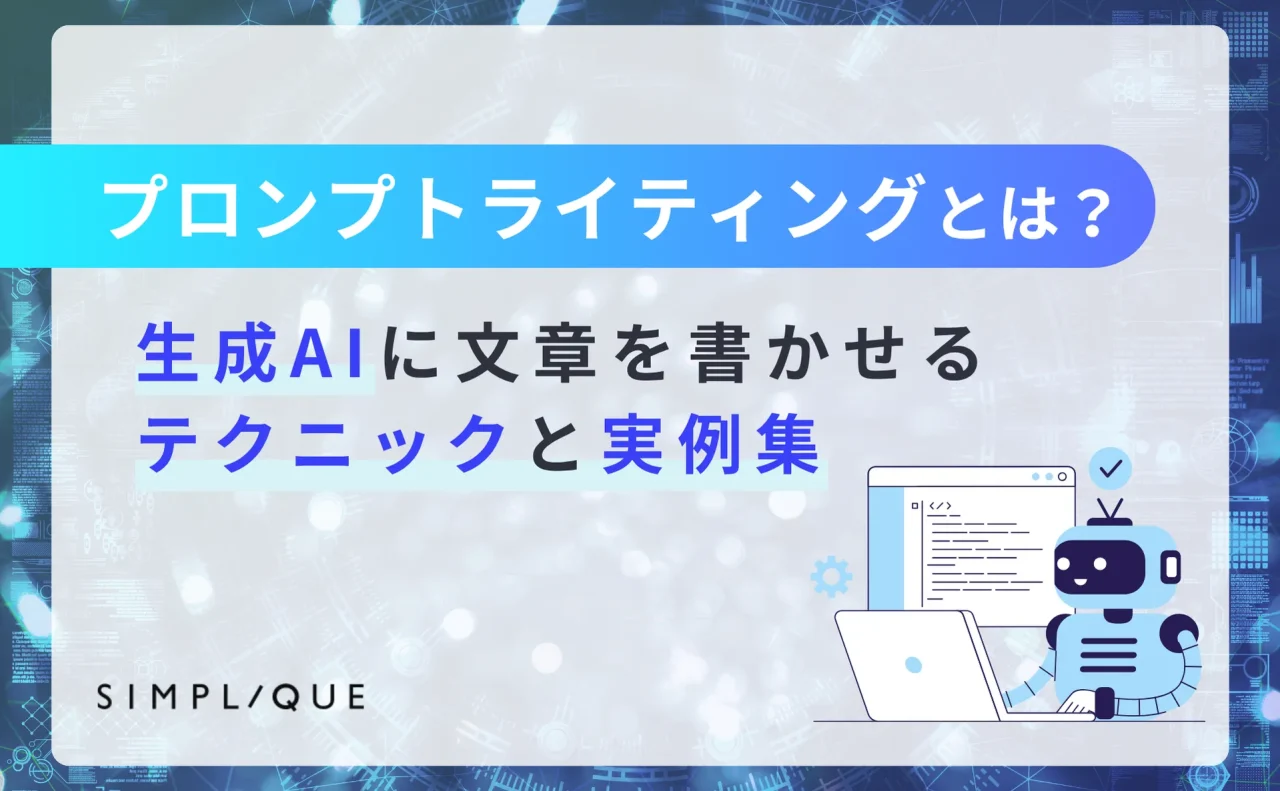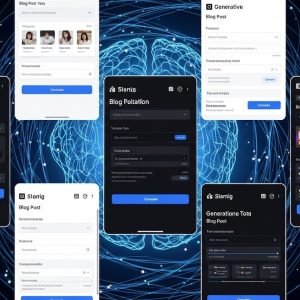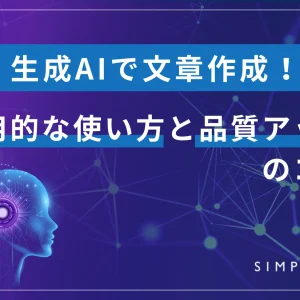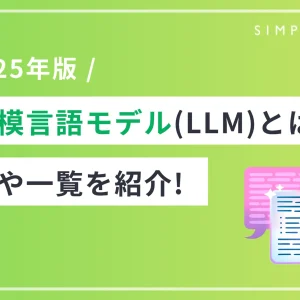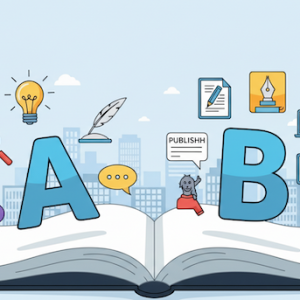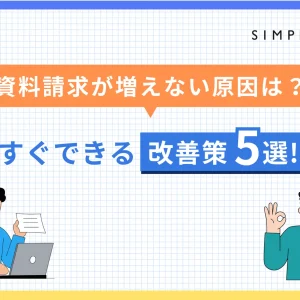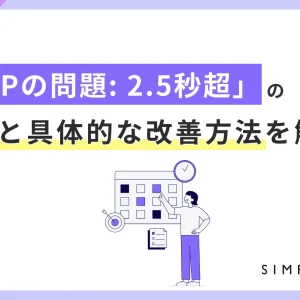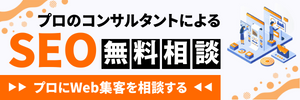生成AIを活用して文章を作成する機会が増える中で、注目されているのが「プロンプトライティング」という手法です。これは、AIに対して適切な指示文(プロンプト)を与え、意図通りのアウトプットを引き出すためのライティング方法を指します。本記事では、プロンプトの設計方法から具体例、よくある失敗と改善のコツまで、初心者にも分かりやすく解説します。
目次
プロンプトライティングとは?

生成AIを効果的に活用するうえで不可欠なスキルが「プロンプトライティング」です。このセクションでは、その基本的な意味や役割、通常のライティングとの違いについて解説します。
プロンプトの定義と役割
プロンプトとは、AIに対して「どのような出力をしてほしいか」を指示する文章のことです。
たとえば、「中学生にもわかるように、AIについて300文字で解説してください」といった文が該当します。
プロンプトは生成AIにとっての“命令文”であり、その内容によって出力される文章の構成やトーンが大きく変わるという特徴があります。つまり、質の高いプロンプトを設計できれば、それだけ質の高い文章を生成しやすくなるということです。
なぜプロンプトが文章品質に影響するのか
生成AIは、確率的に「もっとも自然に続きそうな単語や構文」を選んで出力する仕組みです。そのため、プロンプトがあいまいだと、内容がぼやけたり、意図しないトーンになったりすることがあります。
たとえば「SEOについて書いて」という指示では情報が漠然としすぎており、出力の精度も安定しません。一方で、「SEOの基本を初心者向けに、500文字でやさしく解説して」といった具体的なプロンプトを使うことで、より的確で意図に沿った文章が得られやすくなります。
通常のライティングとの違い
通常のライティングでは、構成や文体、語彙の選び方まで、すべて人間が自ら考えて文章を組み立てます。一方、プロンプトライティングでは、自分で文章を書くのではなく、「どのような構成で、どのような文体で書いてほしいか」をAIに指示することが主な役割となります。
- ライティング=書く力
- プロンプトライティング=書かせる力
このように、プロンプトライティングでは文章力そのものよりも、「設計力」や「指示力」といった、情報を伝える力・引き出す力が問われるのが大きな特徴です。
良いプロンプトの条件と設計の基本
生成AIに期待通りの文章を出力させるには、プロンプトの設計が何よりも重要です。このセクションでは、AIからより精度の高い出力を引き出すために押さえておきたい、プロンプト設計の基本ポイントを解説します。
明確な目的設定と読者想定
まず重要なのは、「誰に」「何を」伝えるかをプロンプト内で明確にすることです。
- 誰に:初心者向け、中学生向け、マーケター向け、など
- 何を:◯◯の概要、メリット、注意点、使い方、など
この2点を設定するだけで、AIは文体や語彙の選び方、情報量などを自動的に調整し、より適切な出力をしやすくなります。逆に、読者層や目的が曖昧なままだと、トーンや内容が不安定になりがちです。
書き方テンプレートと構文例
プロンプトには、汎用的に使える「型」があります。これを押さえておくと、毎回ゼロから考える必要がなくなり、効率的かつ安定した設計が可能になります。
【基本テンプレート】
「◯◯について、【読者層】向けに【目的】を【制限(文字数・構成)】で説明してください。」
【例】
「SEOの基本について、初心者向けにわかりやすく、500文字以内・ですます調で解説してください。」
このように構造が整理されたプロンプトは、AIの理解度が高まり、より期待に近いアウトプットを得ることができます。
出力形式・文体・トーンの指定
プロンプトを設計する際は、以下のような「形式条件」を具体的に指定しておくと、AIが意図を正確にくみ取りやすくなります。
- 文体:ですます調、断定口調、フレンドリー、など
- 出力形式:箇条書き、見出し付き、構成案、など
- トーン:親しみやすく、論理的に、やさしく、ユーモラスに、など
たとえば「小学6年生でも理解できるように」といった曖昧な表現よりも、「〜を300文字以内で、箇条書きで3つのポイントに分けて説明してください」といったように、文量・形式・構成の具体的な制約を含めたプロンプトの方が、より期待に近い出力を得やすくなります。
| 観点 | 良いプロンプト例 | 悪いプロンプト例 |
|---|---|---|
| 目的 | 「◯◯を初心者向けに解説」 | 「◯◯について教えて」 |
| 出力形式 | 「500文字以内、ですます調、3つの見出し構成」 | 「わかりやすく書いて」 |
| 読者想定 | 「中学生にもわかるように」 | 読者層の指定なし |
| トーン・文体 | 「やさしく、親しみやすく」 | 指定なし/トーンがぶれる |
用途別プロンプト例と解説

プロンプトライティングは、使う場面によって最適な構文や指示内容が異なります。このセクションでは、代表的な文章の用途ごとに、実際のプロンプト例とその意図、そして出力イメージを紹介します。
ブログ・SEO記事向け
目的:検索キーワードに基づいて構成された読みやすい記事を生成すること
【プロンプト例】
「“プロンプトライティング”というキーワードで検索上位を狙う記事構成を考えてください。h2〜h3の見出し案を、想定文字数付きで提示してください。」
【出力例(抜粋)】
- h2 プロンプトライティングとは?(800文字)
- h2 良いプロンプトの条件と作り方(900文字)
【解説】
SEO向けプロンプトでは、「キーワードの指定」「見出し構成(h2・h3など)」「想定文字数」といった具体的な条件を明示するのがポイントです。
Googleの検索意図に沿った構成をAIに設計させるイメージでプロンプトを作ると、検索上位に近づく精度の高い記事案を生成できます。
メール・SNS・広告文向け
目的:短く印象的な言葉で、ターゲットの関心を引き、行動を促すこと
【プロンプト例】
「新発売のWebライティング講座を、SNS向けに3パターンのキャッチコピーで紹介してください。親しみやすく、20〜30代向けに。」
【出力例(抜粋)】
- 文章が苦手でも、AIと一緒なら大丈夫!
- プロンプト次第で“伝わる”が変わる!
- 書くのはもうAIに。学ぶのはあなたの思考術。
【解説】
SNS投稿や広告文では、短さ・わかりやすさ・インパクトが重要です。
そのため、プロンプトの中で「文量」「トーン」「出力パターン数」などを具体的に指定することが鍵となります。あらかじめ条件を明示することで、表現の幅とターゲットへの訴求力を両立しやすくなります。
業務文書・マニュアル向け
目的:社内文書や手順書を正確・簡潔に整えること
【プロンプト例】
「社内向けに“プロンプト設計マニュアル”を作成したいです。5つのステップで、見出し+説明の形式でまとめてください。口調は敬体でお願いします。」
【出力例(抜粋)】
- プロンプトの目的を明確にする
→ 使用目的を明文化し、AIに伝わりやすくします。 - 出力形式・トーンを決める
→ 箇条書き、敬体、親しみやすく…など、条件を明示します。
【解説】
業務文書では、「情報の正確さ」「段階的な説明」「丁寧で統一された口調」が求められます。
そのため、プロンプト設計時にはフォーマットの指定(見出し+説明)や、トーン・スタイルの明示(例:敬体、丁寧語)が不可欠です。読み手の理解を助けるためにも、形式面の指示はしっかり盛り込むようにしましょう。
プロンプトライティングを改善するコツ
初めて作成したプロンプトでも、ある程度の出力は得られます。しかし、より自分の意図に沿った品質やスタイルに近づけるには、プロンプトを“磨き込む”作業が欠かせません。このセクションでは、プロンプトをブラッシュアップするための実践的なコツを紹介します。
再生成とプロンプト調整の繰り返し
生成AIの出力は、“一発で完璧”を狙うよりも、“試行錯誤しながら調整する”ことが前提です。たとえば、以下のような要望をAIに伝えながら微調整していくのが基本です。
- 「もっと簡潔にまとめて」
- 「見出しを1つ追加して」
- 「語尾が固いので、やさしい言い回しにして」
このように、出力を見ながらプロンプトを微調整するのが基本です。最初は大雑把でも、少しずつ意図をAIに伝えることで、段階的に精度を高めていく感覚で取り組むのがコツです。
トーン・言い回しの微修正方法
文章のトーンや言い回しなど、細かなニュアンスを調整したい場合は、出力の「一部だけを修正する」リクエストが効果的です。たとえば、以下のような具体的な指示が挙げられます。
- 「この段落だけ敬体に直して」
- 「“〜です”調に統一してください」
- 「ここに箇条書きを追加してください」
出力全体を最初から作り直すより、こうした“部分修正”の指示を活用することで、作業効率が上がり、AIの出力も意図に近づけやすくなります。
フィードバック付き出力の使い方
AIに対して「どこが良くなかったか」「どう改善してほしいか」を明確に伝えると、次回以降の出力がより意図に近づきやすくなります。たとえば、以下のようなフィードバックが有効です。
- 「この文章は全体的に抽象的です。もっと具体例を入れてください。」
- 「見出しはあるものの、説明が短すぎます。各セクション200文字以上にしてください。」
このようなフィードバックをプロンプトの中に組み込んで伝えることで、AIが次回以降の応答に反映させやすくなります。“自分なりの好み”をAIに学習させていく感覚で使うと、やり取りがスムーズになり、出力の質も安定してきます。
よくある間違いと注意点

プロンプトライティングは一見シンプルなようで、実はつまずきやすいポイントが多数あります。このセクションでは、初心者が陥りやすい典型的なミスや、日常的な運用における注意点を整理して解説します。
曖昧な指示による誤生成
最も多い失敗は、プロンプトの曖昧さによって、意図しない出力が生成されることです。たとえば以下のような指示は、抽象的すぎてAIには解釈が難しくなります。
- 「やさしく書いて」→ どの程度?誰向けのやさしさ?
- 「面白く」→ ギャグ?エンタメ風?誇張表現?
こうした主観的・感覚的な表現だけのプロンプトでは、AIには伝わりづらく、出力のばらつきが大きくなります。「誰向けに」「どんな目的で」「どんな形式で」を明確にすることが重要です。
「小学生でもわかるように、3つの事例を使って説明してください」のように、読者層+構成要素+トーン指定をセットで伝えましょう。
情報の正確性とプロンプトの責任
生成AIの出力は、「もっとも自然に続きそうな言葉の予測」に基づいたものです。そのため、出力された文章が事実に基づいているとは限りません。たとえば、次のようなリスクがあります。
- 実在しない統計や人物を挿入してくる
- 意図と違う論調になる(例:中立性が欠ける)
そのため、プロンプトの設計者=利用者が、出力された内容のファクトチェックと責任を担う必要があります。
注意点:
- 専門的な内容を扱う場合は、情報元や根拠の指定も忘れずに明記する
- 「事実ベースで」「出典付きで」といった具体的な指示を加えることで、精度や信頼性を高める
プロンプトライティングは、「書かせること」が目的ではなく、「書かせた後に、どう検証し、どう活用するか」までを含めたプロセスです。AIを使いこなすうえで、常にこの視点を忘れないようにしましょう。
まとめ
プロンプトライティングは、生成AIを自在に使いこなすための基本技術です。単なる指示文ではなく、構成・目的・文体を明確に設計することで、AIから得られるアウトプットの質は飛躍的に高まります。
さらに、再生成・調整・フィードバックといった試行錯誤のプロセスを通じて、AIとの協働スキルも磨かれていきます。生成AIを「ただのツール」として使うのではなく、「自分の思考を補完してくれるパートナー」として活用する。その第一歩が、プロンプトライティングなのです。
生成AIを活かして、コンテンツ制作の効率とクオリティを一段高めたいとお考えの方は、シンプリックにぜひご相談ください。現場で活きるプロンプト設計のコツや改善のポイントをもとに、成果につながる情報発信を一緒に設計していきましょう。

シンプリックのSEO事業全体を監修。海外のマーケティングカンファレンスにも足を運び、最新のSEOおよびコンテンツマーケティング動向に精通。「競合が少なくコンバージョンを生み出せるキーワードの選定」「読みやすくロジカルな記事コンテンツの監修」を得意としています。
【実績】2005年に設立した株式会社ブルトア(サクラサクマーケティング株式会社)では、多数のクライアント、パートナー企業の検索エンジン集客に貢献し、SEO事業を年商7億規模に伸張させる。その後、設立した株式会社シンプリックでは、自社の海外通販事業を検索エンジンからの集客により2年で月商3000万規模に拡大。