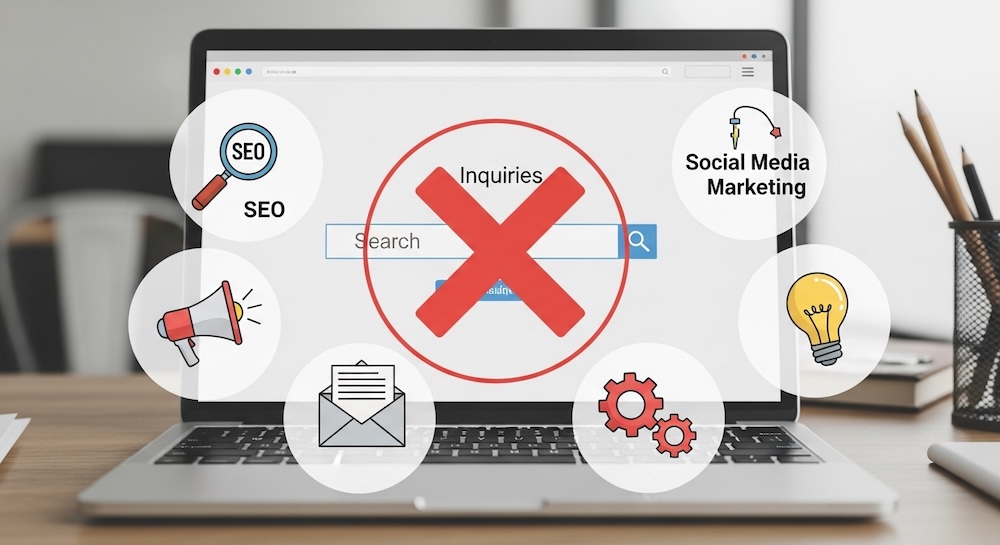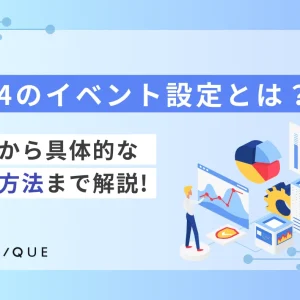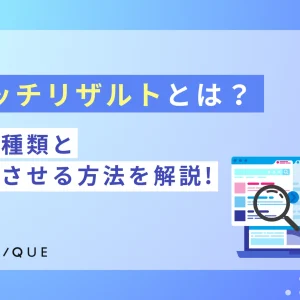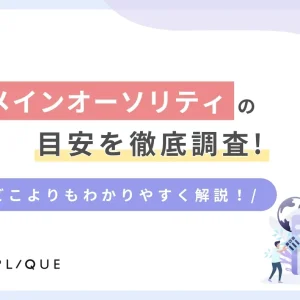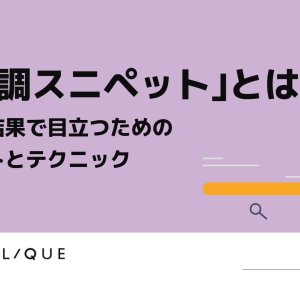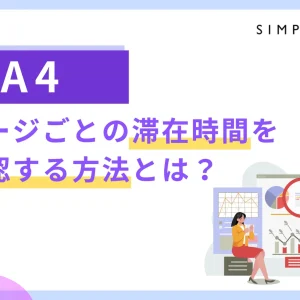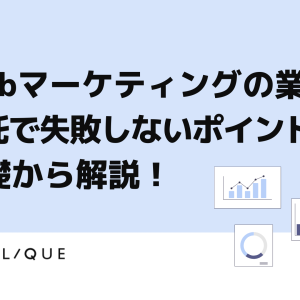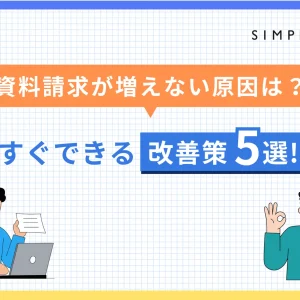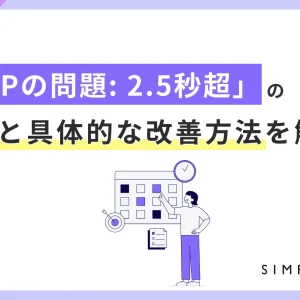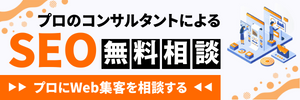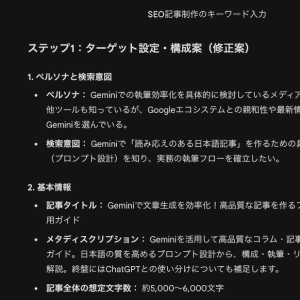ホームページを公開してしばらく経つのに、「お問い合わせがまったく来ない…」と悩んでいませんか?
アクセスはあるのに問い合わせが発生しない、あるいはアクセス自体も少なく期待していた成果が出ていない──こうした状況は、多くのサイト運営者が一度は経験する課題です。
実は「問い合わせが来ない」には、明確な原因が存在します。フォームの使いにくさや導線設計の不備、信頼感を与えられていないページ構成など、ユーザーが行動を起こせない要素が潜んでいるのです。
本記事では、ホームページから問い合わせが来ない代表的な原因を整理し、すぐに実行できる改善施策を5つご紹介します。
なぜ「問い合わせが来ない」のか?

問い合わせが来ない理由は、「需要がない」からではなく、多くの場合ユーザーが“行動しにくい状態”に置かれていることにあります。
ここでは特によく見られる3つの課題を取り上げ、それぞれの問題点を整理していきます。
問い合わせ導線がわかりづらい
ユーザーが「問い合わせたい」と思っても、どこからアクションすればよいのか分からなければ、そのまま離脱してしまいます。
特に、ファーストビューやページ下部に目立つCTAが配置されていない、内部リンクが不足しているといったケースは要注意です。問い合わせボタンの設置場所・文言・視認性を今一度見直し、ユーザーが迷わず行動できる導線を整えることが重要です。
ユーザーの不安を解消できていない
「問い合わせたらしつこく営業されそう」「個人情報が悪用されるのではないか」といった心理的ハードルを軽視してはいけません。こうした不安が残っていると、どれだけサービスに興味を持っていても行動にはつながりません。
企業情報や実績、料金の明記、プライバシーポリシー、SSL対応の表示など、“安心感を与える情報”を適切に配置することが欠かせません。信頼できる証拠があるだけで、ユーザーの警戒心は和らぎ、問い合わせ率は大きく変わります。
| ユーザーの不安 | 対処の例 |
|---|---|
| 問い合わせたらしつこく営業されそう | ・「強引な営業はいたしません」と明記・問い合わせ前後の対応フローを提示 |
| 個人情報が悪用されるのではないか | ・プライバシーポリシーを明記・SSL対応の表示でセキュリティを強調 |
| 会社やサービスの信頼性がわからない | ・企業情報や実績を掲載・導入実績・顧客ロゴ・レビューを提示 |
| 料金が不透明で後から高額請求されるのではないか | ・料金体系を明示・追加費用の有無を明記 |
CVポイントが記事の流れに合っていない
コンテンツの流れと無関係にCTAが挿入されると、ユーザーは違和感を覚え、スムーズな行動が妨げられます。
たとえば、課題の提示や解決策の提案がない段階で、いきなり「無料相談はこちら」と表示されても、読者はまだ行動する準備が整っていません。ユーザーの理解や共感が深まった“適切なタイミング”でCTAを提示することが重要です。自然な文脈の中で「次の一歩」を促す導線を設計すれば、違和感なく行動につながりやすくなります。
よくある失敗パターンとその対処法
多くのサイトが成果を逃してしまう背景には、いくつかの共通パターンがあります。
ここでは特に頻出する3つの問題を取り上げ、それぞれに対する具体的な改善方法を紹介します。
CTA文言が弱い・曖昧
ユーザーの行動を促すには、「何を得られるのか」を具体的に伝えることが欠かせません。
「こちら」や「詳しくはコチラ」といった曖昧な表現では、ユーザーの期待感を高められず、行動に結びつきにくくなります。以下の表で、良い例と悪い例を比較してみましょう。
| 項目 | 良いCTAの例 | 悪いCTAの例 |
|---|---|---|
| 文言 | 「無料で資料ダウンロード」 | 「詳しくはこちら」 |
| 具体性 | 提供内容と行動後のメリットが明確 | 曖昧で目的が伝わらない |
| 誘導タイミング | 読者の関心が高まった直後に表示 | 導入直後や唐突に表示される |
ユーザーがメリットを即座に理解できる表現へ修正することで、“今行動する理由”を与えられ、CV率の改善が期待できます。
フォームの使い勝手が悪い
フォームが長すぎたり、入力しにくかったりすると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。
特にスマホ表示では、「必須項目が多すぎる」「エラー表示がわかりにくい」「送信後の完了画面が曖昧」といった課題が頻出します。これらは小さな不便に見えても、CVRを大きく下げる要因となるため要注意です。フォーム改善はUI/UX全体の中でも最優先で取り組むべきポイントと言えるでしょう。
改善のポイント:
- 入力項目を最小限にする(名前・メールアドレスのみなど)
- スマホでの表示最適化
- 入力補助(例:住所自動入力など)を導入
コンテンツと問い合わせの整合性がない
記事やページの内容と、そこに設置されたCTAがマッチしていないと、ユーザーは違和感を覚え、行動につながりません。たとえば、課題の説明だけをしている記事で突然「無料相談はこちら」と促されても、読者はまだ相談段階に達していないケースが多いでしょう。こうした状況では、ユーザーの関心レベルに合わせて「次に読みたい関連情報」「より具体的な事例・資料」へ誘導するのが有効です。段階的に信頼を積み上げながらアクションを促す設計が、自然な問い合わせにつながります。
Googleサーチコンソールでチェックすべきポイント

「問い合わせが来ない」原因を特定するには、感覚ではなくユーザー行動や流入の“数値”を確認することが不可欠です。
Googleサーチコンソールを活用すれば、流入キーワードやクリック率、ページの表示状況などを無料で把握できます。ここでは、必ずチェックしておきたい3つの観点を紹介します。
流入しているキーワードを確認する
最初に確認すべきは「検索パフォーマンス」レポートです。
ここでは、どのキーワードで流入しているのか、どのページが表示・クリックされているのかを把握できます。もしユーザーの検索意図とコンテンツの内容がずれていれば、クリックが発生しても問い合わせには結びつきません。
狙いたいキーワードとページ内容が一致しているかを再検証し、必要に応じてタイトルや構成を改善することが重要です。

離脱率の高いページを特定
離脱率が高いページは、ユーザーが“期待外れだった”と感じた可能性があります。
理由としては 「情報が足りない」「内容が薄い」「次にどうすればいいかわからない」などが考えられます。こうしたページでは、導線・コンテンツ構成・CTAを重点的に行うことが有効です。
なお、離脱率の確認はサーチコンソールではなく、Googleアナリティクス4(GA4)も併用することで、より精度の高い分析が可能になります。
重要ページがインデックスされているか確認
問い合わせ導線に関連するページそのものが、Googleに登録(インデックス)されていないケースも少なくありません。
サーチコンソールの「カバレッジ」レポートを確認すれば、除外やエラー扱いとなっているページを一覧で把握できます。特に「検出-インデックス未登録」や「クロール済み-インデックス未登録」と表示される場合は要注意で、サイト構造や内部リンク設計に課題がある可能性が高いです。

今すぐできる改善施策5つ
問い合わせ数を増やすには、まず小さな改善を“すぐに”実行することが鍵です。
ここでは、コストや時間をほとんどかけずに取り組める施策を5つ厳選しました。
①問い合わせページへの内部リンク強化
サイト内の主要ページから問い合わせページへ、スムーズに誘導できているでしょうか。
関連記事やサービス紹介ページの末尾に「お気軽にご相談ください」といった文言で内部リンクを挿入するだけでも、CV率は向上します。特にスマホではページ移動の手間が大きいため、1クリックで遷移できるシンプルな動線設計を意識しましょう。
②CTAの文言・位置見直し
目立っていないCTAや抽象的な表現は、ユーザーの行動を妨げる要因になります。
「無料で試す」「30秒で登録完了」など、具体的でメリットが伝わる表現に変更し、さらに視線が集まりやすい場所(ファーストビューや記事下部など)に設置しましょう。
③フォーム項目の最小化
「入力が面倒」という要素は、ユーザー離脱の典型的な原因の一つです。
不要な項目を削り、メールアドレスと名前のみといった最小限の構成にするだけでも、CV率が改善されるケースは少なくありません。BtoBにおいても、「最低限の連絡先」から関係をスタートする戦略は有効です。
④安心感のある導線設計
「問い合わせても大丈夫だろうか?」という心理的なハードルに配慮する工夫が必要です。
たとえば 「営業は一切いたしません」「個人情報は安全に管理しています」といった安心材料をCTAの近くに添えるだけでも、ユーザーの不安を和らげ、問い合わせ率の向上につながります。
⑤ユーザーレビュー・事例の提示
「他の人も問い合わせている」という事実は、ユーザーの行動を後押しする強力な材料になります。
導入事例やお客様の声をCTAの直前やフォーム横に配置すれば、信頼性が高まり、安心感を持ってアクションしやすくなります。特に権威性や実績の提示は、初回接点における説得力を大きく高めるポイントです。
中長期で行うべき改善施策

短期施策で一定の成果が見え始めたら、次は“仕組み化”と“継続的な改善”にシフトする段階です。
ここでは、問い合わせ数を安定的に伸ばし、成果を持続させるために欠かせない2つの施策を紹介します。
ユーザー心理に沿ったコンテンツの構成
ユーザーが「読み進めやすい」「信頼できる」と感じる記事構成は、問い合わせにつながる可能性を大きく高めます。
たとえば、「課題の提示 → 解決策の提案 → 具体的な支援内容 → CTA」という流れで組み立てれば、心理的抵抗が少なく行動までのストレスも軽減され、CVR向上が期待できます。
さらに、情報の粒度や文体をペルソナに合わせて調整することで、理解しやすさと共感が生まれ、行動を後押ししやすくなります。
リードナーチャリング施策の設計
「すぐには問い合わせに至らないユーザー」を継続的にフォローし、段階的に育てる仕組みがあると、中長期な成果につながります。
具体的には、メールマガジンやホワイトペーパー、セミナー案内などを組み合わせ、少しずつ信頼関係を築いていくことが重要です。
さらに、閲覧履歴や興味分野に基づいたパーソナライズ配信を行えば、アプローチの精度が高まり、問い合わせの確度を一層引き上げることができます。
まとめ
「問い合わせが来ない」問題は、サイトの設計やコンテンツの質、導線のわかりやすさ、さらにはユーザー心理まで、複数の要因が絡み合って生じます。しかし、小さな改善であっても正しく取り組めば、問い合わせ数は着実に増加していきます。
まずは「今すぐできる5つの施策」から実行し、短期的な改善効果を確かめながら、中長期的な施策で基盤を固めることが重要です。自社に合った改善策を知りたい方は、まずはお気軽にシンプリックまでご相談ください。