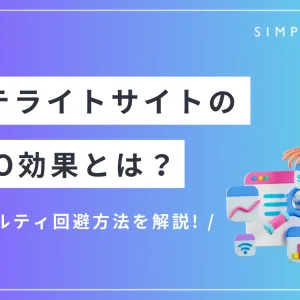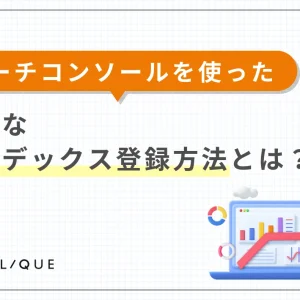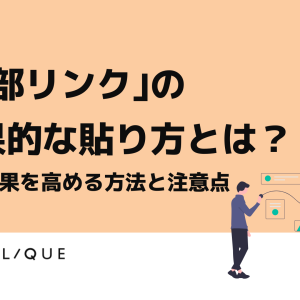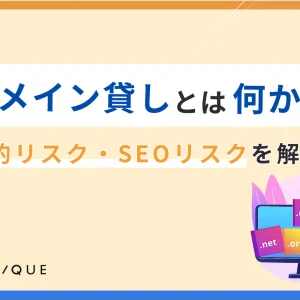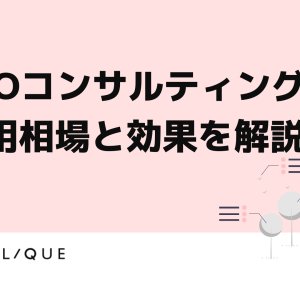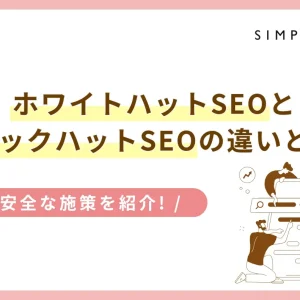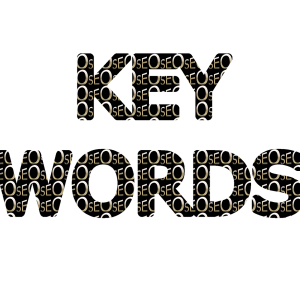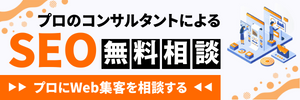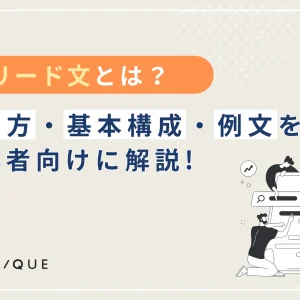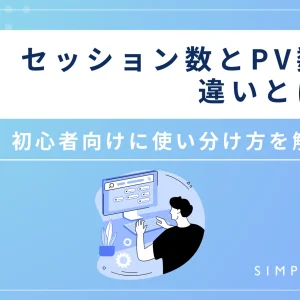SEO施策で、サイトの更新頻度はどのくらいに保つべきか迷った経験はありませんか?
「とりあえず一定の頻度を保ったほうがいいのでは?」と考え、一定の頻度で記事を更新できるよう制作・掲載スケジュールを組んでいる方も多いはずです。
本記事では、サイトの更新頻度とSEO評価の関係性について解説します。更新頻度を上げれば検索順位は上がるのか、更新頻度よりも重要な取り組みはあるのか。SEO運用の現場で出くわす疑問にお答えします。
「そもそもSEOについてあまり理解できていない」という方は、以下の記事も併せてお読みください。
【2023年最新・完全版】SEO対策とは?初心者向けに「どこよりも」わかりやすく解説!
目次
更新頻度とSEO評価に直接的な関係はない
結論からお答えすると、サイトの更新頻度とSEO評価に直接的な関係性はありません。つまり更新頻度を上げたとしても、それだけで検索順位が上がることはないのです。
その代わりに重要なことは『サイト内のコンテンツの質』です。ユーザーの検索ニーズを満たす質の高いコンテンツを作ることが、検索エンジンに評価される上で最も重要です。
サイト運営における更新の定義
サイト運営における「更新」とは、以下のいずれかを満たすアクションのことです。
- サイト内に新規ページを掲載する
- 既存の掲載ページを部分的に修正する
「サイト内に新規ページを掲載する」は新規コンテンツを追加することを意味します。「既存の掲載ページを部分的に修正する」は、具体的には以下の行為をさします。
- 更新頻度を保つためにページ内データの一部や添付画像を差し替える
- ページの更新日を最新にするために特に目的なく一部を修正する
- 更新頻度を保つために検索ニーズを満たさない短文のコンテンツを掲載する
上記はいずれもコンテンツの質を改善しようとして起こしたアクションではありません。単に更新頻度を上げることを目的としたものです。
更新頻度そのものを目的化しない
このようにサイトの更新頻度を上げることだけを目的にしても、SEO評価は上がりません。検索結果の上位に表示されるのは、検索ニーズを満たす高品質なコンテンツです。つまり、「質の高いコンテンツ」を「いかに更新頻度高く」掲載していくのかを考えるべきなのです。
確かに、QDFアルゴリズム(最新の情報が優先されること)に該当するようなトレンド性・速報性の高いコンテンツは、ある程度質を軽視しても検索サイトで上位にヒットすることはあるでしょう。しかし、これはあくまで一時的な順位の上昇であり、長期的に見るとサイト全体の評価を下げる可能性もあります。いずれにせよ、低品質コンテンツを頻繁に掲載することは推奨されません。
| 【QDFアルゴリズムとは】 「Query Deserves Freshness」の略で、直訳すると「検索は新鮮さに値する」を意味する。 検索数の増減やSNSでの言及数、ニュースサイトでの話題性などを検索エンジンが総合的に判断し、トレンド性の高いページを上位表示させる検索アルゴリズム。QDFアルゴリズムが適用されやすい検索クエリ(語句)は「地震や天気に関する情報」や「芸能人の話題やスポーツの試合結果」「放送中のドラマやアニメ情報」など |
更新頻度だけを目的にするのはSEO評価に悪影響?
更新頻度だけを目的としてサイトを運用することは、SEO評価に悪影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。
更新頻度だけを考えてしまうと、コンテンツの質が低下したり、同じ内容の記事が重複したりなど、Googleからの評価が下がる事態をもたらします。「更新頻度が重要だ」と感じている人は、SEOのこれまでの歴史をどこかで見聞きし、イメージが残っているのだと思います。
過去にはコンテンツの量産も流行した
「更新頻度がSEO評価に高い効果を発揮する」と考える人がいる原因としては、過去のブラックハットSEOが考えられます。ブラックハットSEOとは、Googleの本質ではなく、抜け道を使って上位表示させる手法全般のことです。
過去には、ブラックハットSEOの1つとして、コンテンツを量産することで上位表示ができた歴史があります。しかし、質の低いコンテンツの量産はユーザビリティを無視する可能性が高く、Google検索エンジンの有用性を低下させます。
そのため、Googleは2012年4月に「ペンギンアップデート」、2012年7月に「パンダアップデート」を実施しました。ペンギンアップデートやパンダアップデートとは、コンテンツの品質低下や悪質なリンク操作を防止するためのGoogleのアルゴリズムのことです。
ブラックハットSEOの1つである「コンテンツの量産」が流行した名残から「更新頻度が高い=SEO評価が高まる」という勘違いを生んでいることがあるのです。
サイト全体の品質が低下しGoogleからの評価が下がる恐れがある
適切なSEO対策には、ユーザーニーズを満たした品質の高い記事の制作が必須です。そのため、更新頻度を最優先にすると、記事の品質低下を招いてしまう恐れがあります。Webサイト内において、品質の低いページの割合が多くなれば、Googleからのドメインに対する評価も下がり、Webサイト全体に影響を与えます。
おすすめの更新・投稿頻度
更新頻度や投稿頻度は、SEO評価に直接的な関係はありません。しかし「更新・投稿頻度の目安を知りたい」と考える人が多いです。適切な更新・投稿頻度の目安を考える際には「ユーザーに有益かどうか」で判断しましょう。
SEOの記事制作では、更新頻度や投稿頻度など成果を出すための要因が複雑に絡み合って「狙ったキーワードで上位表示できるか」が決まります。正しい方法で取り組めなければSEOの成功確率が下がりますので、成功確率を上げたいのであればぜひ弊社のSEO無料相談をご活用ください。SEOで成果を出したいWeb担当者様向けに、プロのSEOコンサルタントがノウハウを伝授いたします。
続いては、SEOの適切な更新・投稿頻度について、新規コンテンツと既存コンテンツの2つに分けて解説します。
新規コンテンツの場合
新規コンテンツの場合は、品質を保ったまま更新・投稿できる頻度で考えることが大切です。更新・投稿頻度を先に決めてしまうと、足かせとなってしまい、コンテンツの質が低下する恐れがあります。
例えば、他のコンテンツと内容が重複していたり、誤字脱字が多いコンテンツはユーザーにとって有益ではありません。ユーザーの有益性を高めるためには、更新・投稿頻度を下げてでも、質の高いコンテンツを作ることを優先しましょう。
また、Googleから評価を得るためには、情報を網羅的にまとめ、関連性の高いキーワードをコンテンツに含めることが大切です。ただ、オリジナリティの有無も評価に大きく影響するため注意しましょう。
参考:低品質コンテンツとSEO | Google検索セントラル | ドキュメント
既存コンテンツの場合
新規コンテンツがGoogle検索エンジンに表示されるまで、公開してから1~2ヶ月程度かかるケースもあります。また、最初は順位が低くても、徐々に順位が高まることもあります。
そのため、順位が低いからといってすぐにリライトするのではなく、すくなくても公開後1ヶ月程度様子を見てから判断するのがおすすめです。
既存コンテンツをリライトすべきかどうか悩んでいるなら、下記表を参考にしてみましょう。
| 状態 | 優先順位 | 詳細 |
| Googleからペナルティを受けている | 高い | Googleのガイドラインに違反している可能性が高いため、早急に対応が必要 |
| Googleに認識されていない | やや高い | Googleにページが認識されていないとユーザーに届けられないため、早急にインデックスするべき |
| コンテンツの情報が最新のものではない | 普通 | Googleは最新かつ良質なコンテンツを求めているため、可能な限り情報を新しくすることが大切 |
| 検索エンジンの1ページ目に表示されている | 低い | すぐに更新する必要はないが、定期的に更新することでより高い順位を目指せる |
上記の表が、更新・投稿頻度の正解ではありません。更新・投稿頻度は、運営するサイトの順位を定期的に測定しつつ、更新すべき理由がある時に適切に更新することが大切です。
また、Googleからの評価が低いコンテンツを放置し、更新すべき時に更新しなければ、サイト全体の信頼性が低下する恐れもあります。質の高いコンテンツの評価を下げないためにも、必要に応じてリライトを行い記事の品質向上をはかることが大切です。
コンテンツSEOで更新頻度よりも重視すべきこと
SEOの観点で評価を上げるには、コンテンツの更新頻度にとらわれることなくコンテンツの質と向き合うことが重要です。ここではコンテンツSEO施策で更新頻度よりも重視すべき、主な取り組みを挙げます。紹介する中から自社サイト運営の優先度を決め、丁寧に対応を進めていきましょう。
コンテンツの質を高める
検索エンジンからの評価を高めるには、コンテンツの質を上げることが最も重要です。この記事に限らず、SEO施策を解説するページではどこでも強調されていることで、すでに認識はしている方も多いでしょう。では、どのような点を意識して記事を制作すればコンテンツの質が高まるのでしょうか。
SEO担当者は、特定のキーワードの検索ニーズを満たすコンテンツ制作に向き合うべきです。
SEOを目的とした記事の制作では、最初に検索エンジン対策を施す検索キーワードを決めます。検索キーワードが決まったら実際にGoogleで検索し、どんなコンテンツが上位表示されているのかを調べ、ユーザーが求めている情報を整理しましょう。
さらに、検索したキーワードと一緒に出てくるサジェストワードも確認し、これから作るコンテンツの構成に関連ワードを入れられるか精査します。
読者視点に立ち「自分が同じ検索キーワードで調べたとき、どんな情報を読みたいか」を考えることも大切です。そのほか、記事を執筆し終えたらすぐ掲載するのではなく、できれば1日以上寝かせることも効果的です。第三者に必ず推敲してもらう意識を持つと、質はさらに上がります。
以下の記事で、質の高いコンテンツの作り方をより詳しく解説しています。
SEOライティング基礎 | 初心者が最高の一記事を作り上げるために
誤った情報や古い情報をリライト
SEO記事は掲載したら終わりではありません。検索ユーザーは常に、最新で正しい情報を求めています。そのため掲載から日数がたち、事実と異なる情報、古くなった情報を含む場合はリライトして最新のものに更新することが大切です。
掲載したSEO記事は、掲載日やキーワード、文章量などが分かるようにExcel、Googleスプレッドシートなどに記録し、一定頻度で情報を確認するルーティーンを日々の運用に組み込みましょう。
サイト運用者のなかにはSEOの効果を高めようと、新しい記事の制作・掲載ばかりにリソースを割く方がいるかもしれません。しかしサイト全体の評価を上げるためには、過去に掲載したコンテンツの見直しにも同じくらいリソースを割くことを意識すべきです。
効果的なリライトの方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
リライトでSEOを強化する!リライトの手順・ポイントを徹底解説
検索順位が低いページのコンテンツの見直し
SEO対策を施した記事は検索キーワードにもよりますが、公開からおよそ3〜6カ月で検索順位が安定してきます。なお検索ボリュームが多く競合性の高いビッグワードであればあるほど、検索結果に反映されるまでに時間がかかります。
掲載から3カ月程度が経過したら、それぞれのコンテンツの検索で何位を獲得しているか確認しましょう。
何位以下をリライト対象とするかはSEO運用者の方針によりますが、上位のコンテンツと比較して不足していると思われる情報を加筆する、ユーザーの理解が深まるよう、図解を挿入するなどの見直しを進めます。
低評価コンテンツを削除またはnoindexにする
過去に公開した記事のうち、検索順位が極めて低いコンテンツ(100位以下)は、リライトするのではなく削除、もしくはインデックス(Googleのデータベースへの登録)しないような対応をして、検索エンジンの評価対象から除くこともひとつの選択肢です。SEO評価はドメインそのものの評価を示す「ドメインパワー」にも影響を受けます。
ドメインパワーは権威の高い良質な被リンクをどれだけ獲得しているか、ドメイン内にどれだけ良質なコンテンツが含まれているかに左右されます。つまり、評価が低いコンテンツが含まれているとドメインパワーを引き下げる要因になってしまうのです。
そのため、リライトしても検索で上位にヒットしないと判断したコンテンツはサイトから削除するか、検索エンジンのクローラーが巡回しないようにするnoindex設定をするといいでしょう。SEO評価の点ではマイナスでもサイトのコンテンツとして必要、またはCV(コンバージョン)獲得のために必要であればnoindex設定をするのがおすすめです。
「E-A-T」を意識したコンテンツを作成する
SEO評価を高めるためには、更新頻度ではなく「E-A-Tを意識したコンテンツ作成」も重要です。「E-A-T」とは「専門性・権威性・信頼性」の略であり、E-A-Tを満たしているコンテンツの方がGoogleからの評価は高まりやすいと考えられています。
| E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-A-T が優れているコンテンツによく見られる要素の組み合わせを使用することは有効です。たとえば、Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。 引用:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | ドキュメント |
E-A-Tを意識したコンテンツ作成をするためには、専門家や業界の著名人に監修・執筆してもらうなどの工夫が必要です。どんな内容のコンテンツを作成するのかだけでなく、誰が監修しているのかも含めることで、専門性や権威性、信頼性を高めやすくなります。
SEO記事は高品質を保ったうえで更新する
記事では、サイトの更新頻度とSEOにおける評価の関係性について解説してきました。
お伝えした通り、サイトの更新頻度を上げること自体に直接的なSEO効果はありません。もし現在、SEO対策でコンテンツの質の改善とは関係ない記事を制作しているのであれば、残念ながら意味はありませんので今後は控えましょう。
ただし仕上げている記事の質がいいのであれば頻繁に更新した方が、より早く検索エンジンに評価されるため効果は出てきます。いずれにしても、SEOを意識した記事制作で重要なのは「コンテンツの質」です。検索ユーザーが求めている情報に答えるような記事を丁寧に作り上げていきましょう。
また弊社シンプリックでは現在、質の高いSEO記事を作り集客を成功させたいWeb担当者様向けに「SEO対策の無料相談」を実施中です。プロのSEOコンサルタントが「成果の出るSEO記事の作り方」や「SEOで成果を出すためのポイント」を伝授しますので、ぜひお申し込みください。
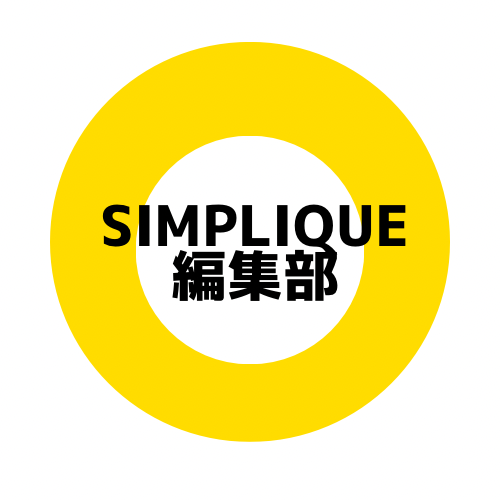
2005年よりSEOに従事、年間3000本以上のSEOコンテンツを制作しているシンプリックコンテンツマーケティング事業部の監修記事です。